「人生がつまらない」
「仕事がうまくいかない」
「給料が上がらない」
社会人として生活していると、様々な悩みが湧いてきますよね。今すぐに解決したけれども、それが現実的には難しく、モヤモヤした思いを抱えたままの人も多いと思います。藁にも縋る思いでインターネット上にある情報を一晩中探したり、忙しい中で書店に行きベストセラー本の内容を見たりしても、なんとなく表面的で腑に落ちないと思っている方も多いのではないでしょうか。
そこで!今回は、社会人の日常生活のお悩みを解決するために役立つ「教養」を身に付けるためにおすすめの本を紹介していきます。
最後まで読んでいただければ、少しだけ前進した自分がいることでしょう。
是非参考にしてくださいね!
社会人のお悩みあるある5つ!

まずは、社会人の典型的な悩みを確認してみましょう。少しでも今のあなたと重なる部分があるのではないでしょうか?
①自分のやりたいことが分からない!

「良い仕事をして世のため人のためにがんばるぞ!」「バリバリ働いて出世するぞ!」と息巻いていたあの頃の自分はどこへ行ってしまったのでしょうか・・・。気づけばルーティーンワークのように同じような毎日を繰り返す日々。テレビやネットを見ていると自分よりも若いのに起業家としてキラキラした姿を見せている人が気になってしまいます。自分がやりたいことをやるために起業を考えようかなと思っても、そもそも自分がやりたいことが思いつきません(泣)。
②忙しくて時間がない!

今の仕事は、人間関係は良好で給料も悪くないです。でも、あまりにも忙しすぎます!早朝に出社して、気づいたら夜の10時になっているなんてことも多いです。帰ったらグッタリして何もできず、疲れが取れないまま翌朝を迎える日々・・・。仕事は好きですし充実感はありますが、自分の人生はこんなものなのでしょうか。この生活が一生続いたらただ歳をとっていくだけで何も残らない気がします・・
③上司が嫌い!

パワハラとまではいきませんが、上司とウマが合いません。言っていることがコロコロ変わり、小さなミスに目くじらを立てて嫌味を言ってきます・・・。明らかに間違っていることがあっても自分を正当化するだけで一切反省する気配がありません。なぜこんな人間が出世して上司をやっているのでしょうか・・・?仕事自体は嫌いではないので、転職を考えてはいませんが、毎日イライラして仕方がありません。
④給料が上がらない!

今の会社に就職してから数年、朝から晩まで働いてきました。先輩方もそうだったみたいです。ある日、たまたま勤続30年の先輩の給料を聞いて思いました。「たったそれだけ?BMW買えないじゃん・・・。」考えてみれば当たり前ですが、今の会社でいくら頑張ったところで、将来は先輩と同じような給料になる可能性が高いです。身動きが取れなくなる前に、自分で事業を起こして大儲けを狙おうか、それとも今の会社で安定を維持していくか、迷っています・・・。
⑤独身で寂しい!

結婚適齢期と言われる年齢にはとっくに突入していますが、未だに結婚できる気配がなありません。そもそも、毎日が家と職場の往復で、休日は疲れてしまって家でyoutubeを見るぐらいしかできないので、異性との出会いもありません。友人たちも、結婚して家庭を築いて幸せそうにしている人達と、自分みたいに独身生活を謳歌(?)している人達に2分されてきました。結婚しない、特定のパートナーもいない状態でこのまま生きていくことはできますし、その方が楽な気もしますが、正直、孤独感や劣等感を覚えずにはいられません・・・。
お悩み別おすすめ教養本5選!
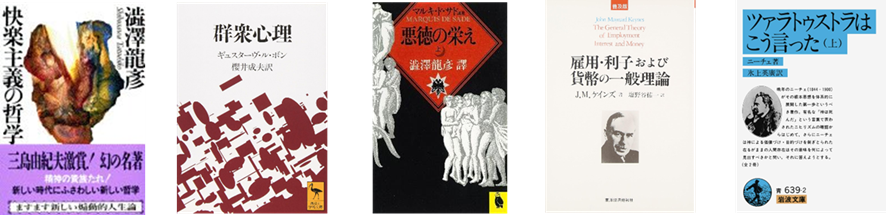
①「自分がやりたいことが分からない!」➡澁澤龍彦著「快楽主義の哲学」
②「忙しくて時間がない!」➡ギュスターヴ・ル・ボン著「群衆心理」
③「上司が嫌い!」➡マルキ・ド・サド著「悪徳の栄え」
④「給料が上がらない!」➡J・M・ケインズ著「雇用・利子および貨幣の一般理論」
⑤「独身で寂しい!」➡フリードリヒ・ニーチェ著「ツァラトゥストラはこう言った(上・下)」
ここで「教養」の意味を確認していきましょう。てっとり早くWikipediaを見てみます。
“教養(きょうよう)とは、個人の人格や学習に結びついた知識や行いのこと。これに関連した学問や芸術、および精神修養などの教育、文化的諸活動を含める場合もある。”(Wikipedia)
抽象的で、いろいろな解釈ができそうです。今回は「個人の人格や精神を向上させるための知恵」ということにしましょう。
では、なぜ「教養」が重要なのか?私たちの内面が変わる事で行動が変わることを期待するからです。例えば、元プロ野球選手で2009年まで東北楽天ゴールデンイーグルスの監督を務めていた野村克也さんは「心が変われば態度が変わる。態度が変われば行動が変わる・・・」と選手に語っていたそうです1)。
1)野村克也著 野村ノート、小学館、2005
教養を身に付けるには、様々な経験を積むことも大事ですが、1000円前後の優れた本を読むことで新たなアイデアを吸収することは非常にコスパが高いと言えます。
今回紹介するのは、最も古いもので1800年代初頭、最も新しいもので1960年代に書かれた古典に属する本です。こういった本は古くさいものとして敬遠されがちです。しかし、歴史を超えてずっと残って読み継がれているというのは、普遍的で永く変わらない真実が記された優れた本である証拠です。
次は、それぞれの本の内容や読み方について、より詳しく紹介していきます。
教養本の読み方を解説!
①「自分がやりたいことが分からない」あなたに
➡澁澤龍彦著「快楽主義の哲学」(文春文庫)
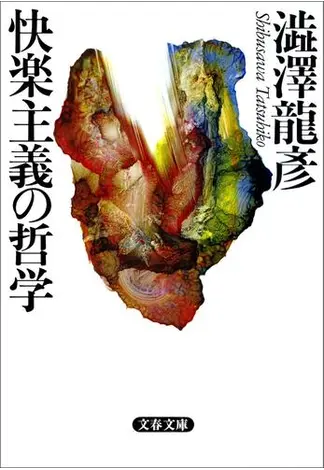
【内容】
著者は、昭和を代表する文学者、哲学者です。当時の高度経済成長を遂げて浮つき始めた日本の社会を皮肉りつつ、人間の生き方について論じています。古代の哲学から人体の構造に至るまで多くのテーマが登場し、様々な快楽を追求することによって人生を謳歌する方法を提案してくれます。その読みやすさとユーモラスな文体はまさに文章の達人。何かに悩んでいる読者が読むと元気づけられます。
【読み方のポイント】
「やりたいことが分からない」と思っている人は、本書の次の1文が参考になるでしょう。
“最初に身も蓋もないようなことをいってしまえば、人間の生活には目的なんかないのです。人間は動物の一種ですから、食って、寝て、性交して、寿命がくれば死ぬだけの話です”
そして、人間には目的がないのだから、自分の欲望を満たし個人的な「快楽」を手に入れることを目指せば良いと、著者は言います。世のためだとか人のためだとか、綺麗ごとは一旦脇に置いておき、まずは自分の本音の欲望に気づくことが大切ということです。それはちっとも恥ずかしいことでも罪深いことでもないからです。私も、この本を読んでから、「高級車が欲しい」「立派な家が欲しい」「高級レストランに行きたい」と欲望が無限に湧き出るようになりました。あとは、まっとうな手段で欲望を叶えるための方法を考えればいいだけです。本書の後半では、快楽を追求した過去の偉人たちの生き様も例示されています。彼らの行動力を見習えば、あなたも快楽追求の旅への一歩を踏み出していけることでしょう。
②「忙しくて時間がない!」あなたに
➡ギュスターヴ・ル・ボン著「群衆心理」(講談社学術文庫)
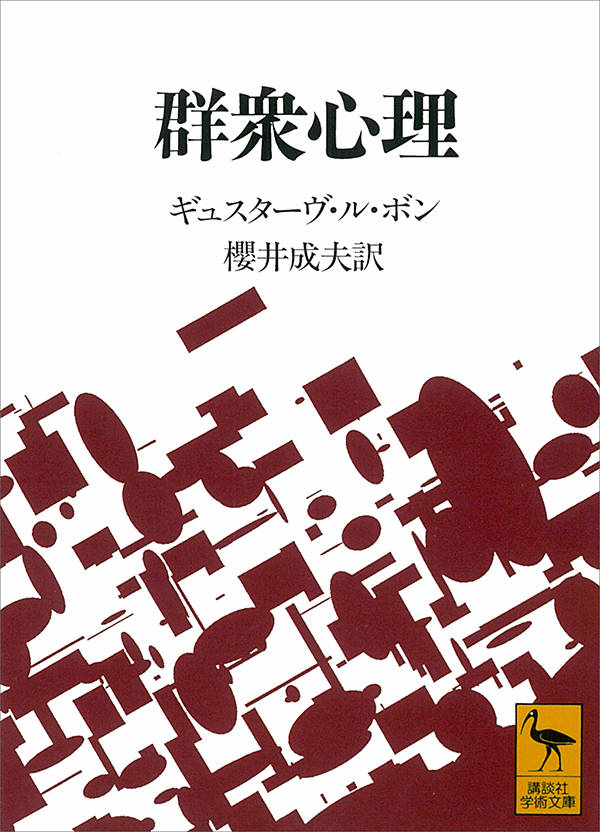
【内容】
著者はフランス出身で医学と心理学を専門とする研究者です。本書では、1800年代末に台頭してきた秩序破壊的な人間の集団を「群衆」と名付け、彼ら彼女らの特徴や行動様式、それらがもたらす社会への悪影響について論じています。著者の天才的な洞察力は、集団化した人間がいかに愚かに振る舞うかを鋭く見抜いています。
【読み方のポイント】
本書で論じられている「群衆」は、知らず知らずのうちに他人や社会に迷惑をかける存在です。その特性として、「周囲に流されやすいこと」「他人と同じような意見を堂々と主張すること」「自己反省能力が低いこと」が挙げられています。「忙しくて時間がないから何もできない」と思っている時点で、自分が「群衆」の一人になっているかもしれない、と考えましょう。最もイメージしやすいのは、SNSを長時間閲覧したり何かを書き込んだりしていることでしょう。「みんながやっているから自分もなんとなくやっている行為」で時間を無駄にしていることは非常に多いです。X(旧Twitter)を見ている時間、youtubeを見ている時間、飲み会で愚痴を話している時間・・・。それらはあなた自身が決心して取り組んでいることでしょうか?現代の「群衆」は常に周囲の情報に流され、時間を無駄にし、GoogleのようなIT企業に搾取されるだけの人生を歩み、何も達成できないまま、気づいたら老人になっているという意見もあります2)。本書を読んで自分の行動を反省することで、自由時間は格段に増えることでしょう。
2)中野剛志著 日本の没落、幻冬舎新書、2018
③「上司が嫌い!」なあなたに
➡マルキ・ド・サド著「悪徳の栄え(上・下)」(河出書房)
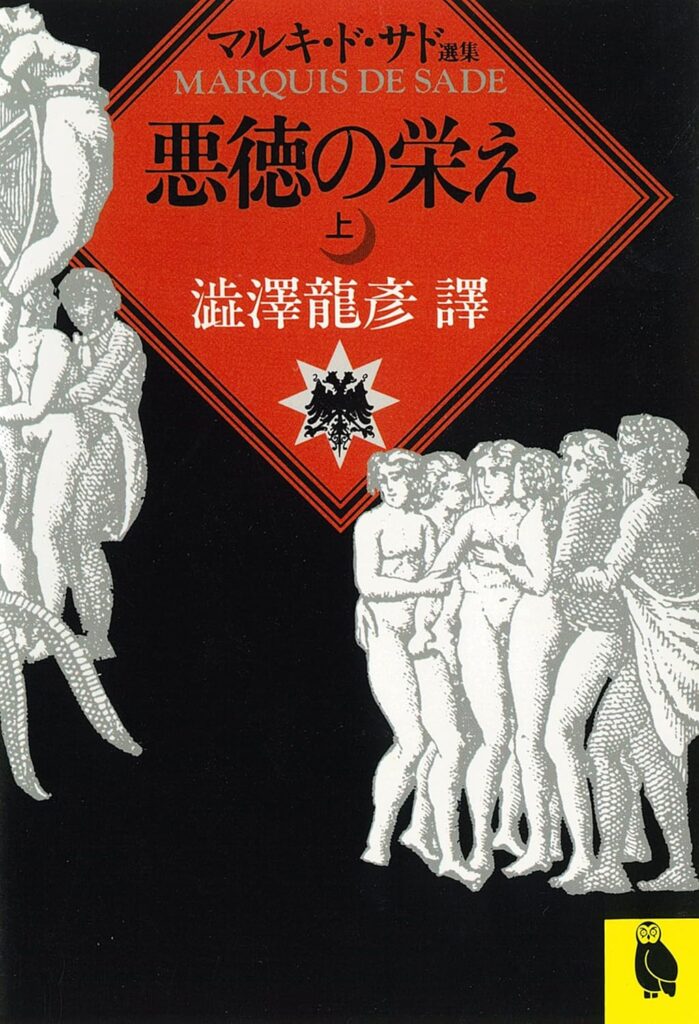
【内容】
マルキ・ド・サドは1700年代にフランスで活躍した小説家です。彼の著作には過激で暴力的な描写が多く、「サディスト」の語源となった人物として有名です。本書は神の存在を徹底的に否定する思想が貫かれ、主人公の美女ジュリエットが様々な極悪非道に手を染めながら一切罰されることなく、多くの仲間に恵まれ人生を成功させていく刺激的なストーリーとなっています。小説の形をとってはいるものの、作者が提唱する思想や社会の在り方を、登場人物を通して語らせることで読者に様々なことを考えさせる哲学書のような本です。
【読み方のポイント】
本書は、フランス文学に精通している人でない限り、初見だと不快感を覚えるような暴力的な行為で溢れています。が、それは表面的な仮の姿。実際には、ほとんどのページで学びがある重厚な哲学的教養書です。主人公ジュリエットとその仲間たちは、常人では考えつかないような数々の悪行を実行し、悪の道に堕ちる喜びやその効能をひたすらに吐露していきます。主要人物の一人で一国の大臣であるサン・フォンは「良心を圧殺して悪を貫くこと」がいかに自分を強くするかを語っています。つまり、この本から学べることの1つは、「良い人は弱い、いつも良い人であってはいけない」ということです。上司にムカついてストレスを溜めてしまっている良い人過ぎるあなたは、本書を読んで「悪徳」を学び、実生活で応用してみると良いでしょう。もちろん、犯罪行為はいけませんし、職場に迷惑をかけてもいけません。例えば、ちょっと冷たすぎるかな?と思うぐらいドライに接してみる、コンプライアンス部門に告げ口しまくる、言い訳を並べて自席じゃない場所で仕事をする、といったことでしょうか。すぐに名案が思い付かなくても、少しずつ良い人を辞めていく勇気、余計な社交から逃れる勇気をくれる、そんな本だと思います。
④「給料が上がらない!」あなたに
➡J・M・ケインズ著「雇用・利子および貨幣の一般理論」(東洋経済新報社)
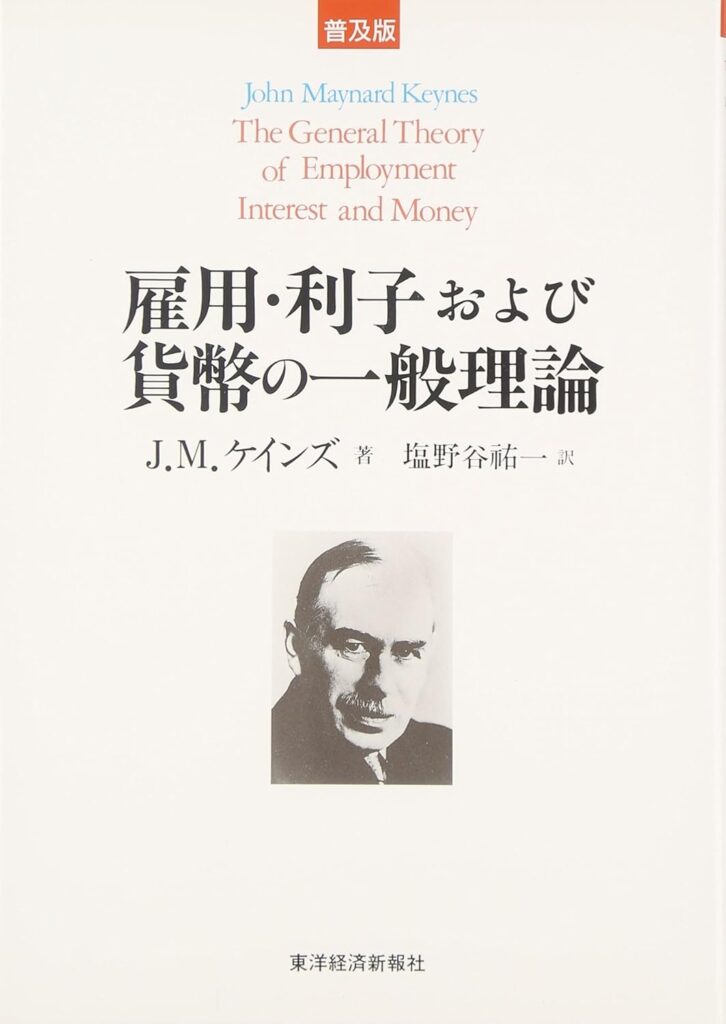
【内容】
J・M・ケインズは1900年代中盤に活躍したイギリスの経済学者です。国際機関の理事なども歴任し、「ケインズ経済学」を創設しました。本書は、経済における「貨幣」や「不確実性」の存在について解き明かし、彼の経済理論を確立する内容となっています。その理論は白眉であり、現代でも通用する色褪せない一冊です。
【読み方のポイント】
ケインズの経済理論は、現代の経済学界では古くて異端とされており、主流派の経済学を扱う多くの経済学者の研究対象からは見向きもされない状況が長年続いています。しかしながら、現代の経済状況はケインズの理論で驚くほど良く説明が可能であり、一方で主流派の経済学ではほとんど何も説明できないというような不思議な事態となっています。ただし、経済学を専門としない一般の人にとって本書は非常に難解であり、私自身も読破を断念しております・・・。そこで、ケインズの経済理論を学ぶための参考書として、評論家の中野剛志氏が著した以下をおすすめします。
・目からウロコが落ちる奇跡の経済教室シリーズ(ベストセラーズ)
・奇跡の社会学(PHP新書)
さて、前置きが非常に長くなりましたが、ケインズの経済理論から推測される「給料が上がらない理由」は「日本の経済政策が30年間誤り続けているから」です。身も蓋もないですが、私たち個人のレベルではどうしようもない問題ということです。まずはそのことを理解しましょう(もちろん、業界構造によって給料が上がりやすい場合とそうではない場合があります)。そのうえで、収入を増やすためにどのような選択をするか、自分自身で決めることが重要でしょう。今すぐ起業して一儲けを狙うか、とりあえずの安定を守って経済政策が改善されるのを待つか、コツコツ副業や投資を頑張るか、などです。ケインズの本や理論から学べることは、経済とは不確実なものなので、将来を予測することは不可能である、ということです。したがって、確実に儲かる方法もないと考えられます。ちなみに私は、株式投資で一発を狙って大損しました・・・。
⑤「独身で寂しい!」あなたに
➡フリードリヒ・ニーチェ著「ツァラトゥストラはこう言った(上・下)」(岩波文庫)
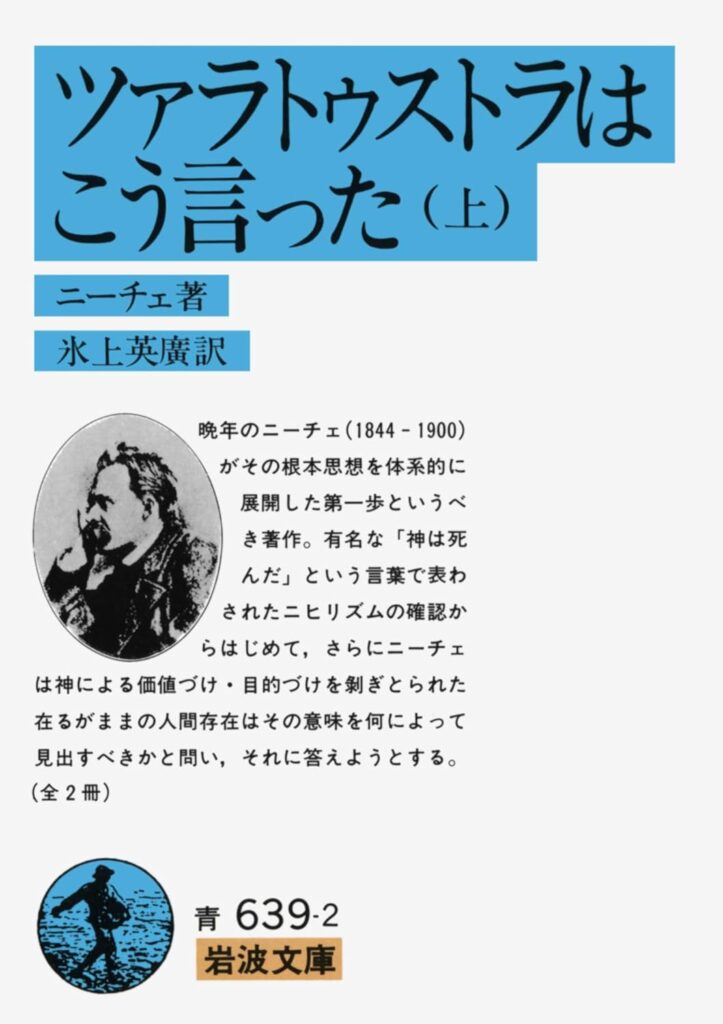
【内容】
世界で最も著名な哲学者の一人であるニーチェが、彼自身の分身であると言われている主人公ツァラトゥストラに、「末人」を脱して「超人」になり、人生の一瞬一瞬を否定せずに生きていくための前向きな思想を語らせる小説形式の本です。生活、職業、男女の性質など、人間生活のあらゆる場面について、他所ではお目にかかれないような鋭い意見が語られます。
【読み方のポイント】
「ニーチェ読みのニーチェ知らず」という言葉があるくらい、ニーチェの哲学書は深く理解するのが難しいです。ニーチェを研究対象とする大学教授ですら読み解けない場合があるとか。その中でも、本書は和訳が素晴らしく、比較的読みやすい部類とされています。「独身で寂しい」という悩みに効くのが、上巻中盤に登場する「子どもと結婚」という章です。ここでは、ニーチェが奨励する結婚の在り方が記されています。少し引用します。
“あなたは若い。そして子供を欲し、結婚を欲している。しかしわたしはあなたにたずねる。あなたは子供を望むことが許されている人間であろうか?”
“まずあなた自身が、身体も魂もしっかり築かれていなければならない”
さらにこの後、多くの甘ったれで夢見がちな人々の結婚生活が実質的には破綻しかけているという現状を厳しく批判していくのですが、あまりにも手厳しい指摘のため割愛します。さて、ここでは、あなたは誰かにパートナーとして選ばれるだけの価値がある人間か?もしくはそうなれるように必死に努力しているか?ということを言っていると解釈できます。表面的なテクニックではなく、自分を見つめ直して努力して、自分の価値を高めることが重要だということでしょう。異性との関係性の構築や維持のための努力は、私たちの苦悩の中でも多くを占めるものです。太っていることがコンプレックスならばダイエットしなくてはいけない、会話が苦手なら練習しなくてはいけない、お金がないなら稼がなくてはいけない、相手が不機嫌なときにどう対応するのが正解か考えなくてはならない。こうした苦悩は悪いものでも今すぐ忘れるべきものでもなく、肯定的に受け入れていくことが最高であるとニーチェは説いています。本書を読むことで、「苦悩=良いこと」という風に思考が転換でき、やがて行動が変わっていくことでしょう。
もっと教養を深めたい方にはこちらの本!
エッカーマン著「ゲーテとの対話(上・中・下)」(岩波文庫)
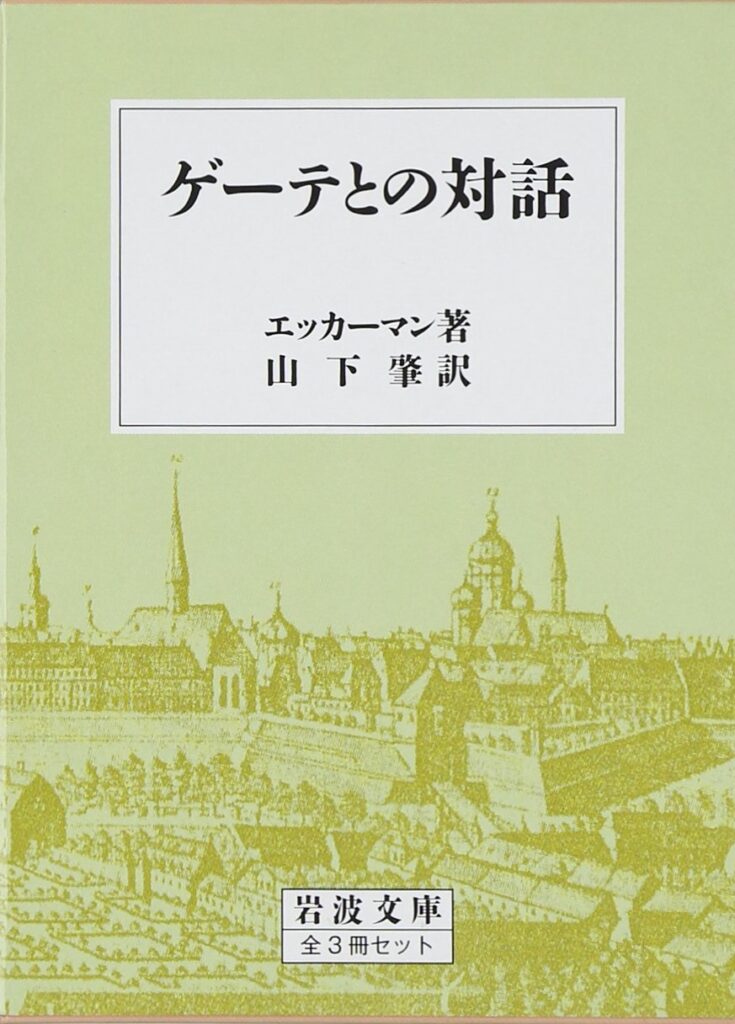
1800年代のドイツを代表する文豪であるゲーテが残した金言の数々を、彼の晩年の弟子もしくは秘書的な存在である青年エッカーマンがまとめた書です。文学から自然科学まで非常に多才であったゲーテの鋭い洞察は、読者の日常生活の様々な場面で応用できる教養を涵養してくれます。3巻構成ですが、どの巻のどのページからでも問題なく読めるので、カバンの中に入れておいて時間のあるときに読むのがおすすめ。いつか、別記事で紹介したいです。
まとめ
本記事では、社会人にありがちな5つのお悩みに沿って、教養が身に付く本と読み方のポイントを紹介しました。
①「自分がやりたいことが分からない!」
➡澁澤龍彦著「快楽主義の哲学」を読んで自分の追求すべき快楽を見つけましょう。
②「忙しくて時間がない!
➡ギュスターヴ・ル・ボン著「群衆心理」を読んで日常生活を省み、無駄な時間がないか点検しましょう。
③「上司が嫌い!」
➡マルキ・ド・サド著「悪徳の栄え」を読んで悪徳を学び、良い人を辞めましょう。
④「給料が上がらない!」
➡J・M・ケインズ著「雇用・利子および貨幣の一般理論」を読んで現実の経済を学び、稼ぐ方法を考えましょう。
⑤「独身で寂しい!」
➡フリードリヒ・ニーチェ著「ツァラトゥストラはこう言った(上・下)」を読んで苦悩することを肯定し、少しずつ自分を向上させていきましょう。
SNSやインターネットで情報がお手軽に手に入れられる現代で、本を読むことは少し大変に感じるかもしれません。しかし、今回紹介した本はいずれも読者に何かしらの衝撃を与えてくれる良本であることは間違いありません。時間や労力をかけて読むだけの価値は大きく、後で振り返ってみると高コスパ・高タイパだったと思えるはずです。
私自身もこの記事を執筆するにあたり読み返してみましたが、いつ読んでも、何回読んでも新たな発見があるスルメのような本ばかりで、改めて多くの人に読んでもらいたいと思いました。ぜひ、手に取って読んでみてくださいね。
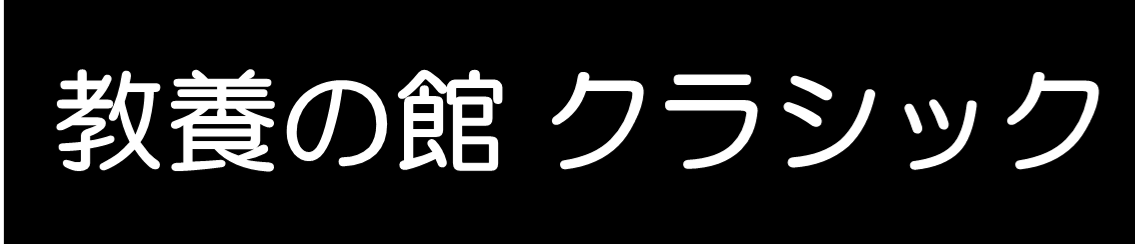
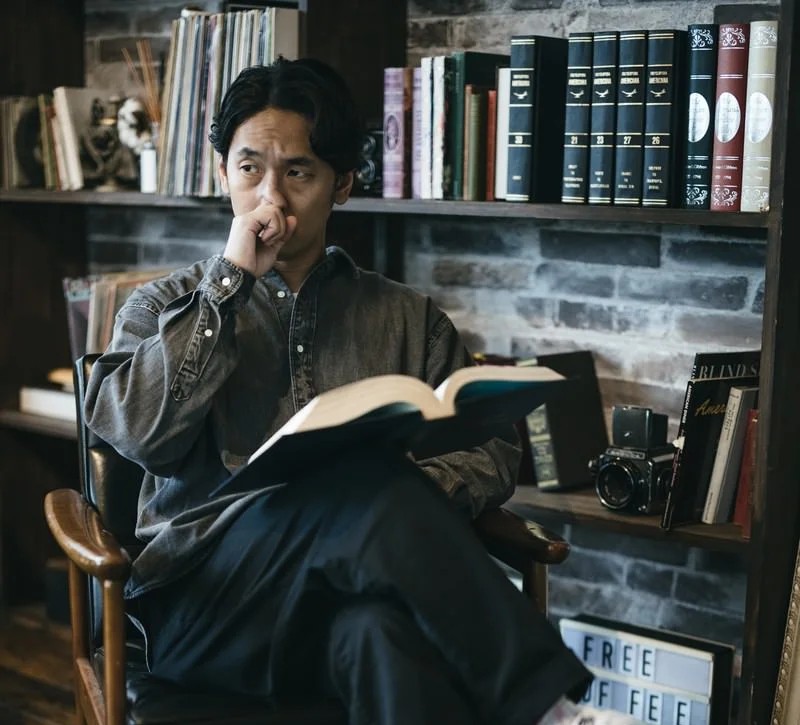
コメント